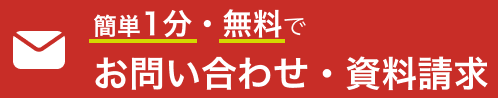星稜高等学校サッカー部
星稜高等学校サッカー部・佐藤悠トレーナーが語る『CLIMB DB活用法』

星稜高等学校サッカー部・佐藤悠トレーナーが語る『CLIMB DB活用法』
――星稜高等学校の河﨑護監督から『CLIMB DB』を導入すると聞いた時、どのような感想をお持ちになりましたでしょうか?
選手と直接顔をあわせることができない時でも、コンディションやケガの状態をスマートフォンのアプリを通して見ることができるので、凄く良いな、助かるなというのが率直な感想です。
――選手達は『CLIMB DB』にどのような項目を入力していますか?
コンディションとケガ、病気や風邪などの状態を入力しています。ケガをしている選手からは「いまの状態はこうです」「今日はこういうリハビリをしました」というコメントが入ります。コメントは私だけでなく、監督やスタッフが見ることができるので、情報の共有がしやすくなりました。コンディションが気になる選手がいる時は、状態を詳しく聞いて監督やスタッフに伝えたりと、『CLIMB DB』がスタッフ間の橋渡しになってくれています。

――佐藤さんは週に何日ほどチームに帯同しているのですか?
――『CLIMB DB』のどの項目をよく見ていますか?
よく見るのはケガの部位や状態とコメント欄です。選手はケガの箇所にマークをつけて、コメント欄にどういうケガをしたかを書いてくれるので、僕の方から「こういう処置をしてください」と返しています。その結果、小さなケガが大きなケガにつながることが少なくなったように感じます。たとえ打撲をしたとしても、直後に適切な処置をすれば、次の日の練習に参加できたりしますからね。

――ケガの現場にいないときでも、適切なケアを遠隔操作で伝えられるのは大きいですね。
そう思います。選手が自己流で処置をしたり、なかには処置をしないこともあるので…。ケガの処置などに関して、選手と『CLIMB DB』のコメント欄でやりとりをする中で、選手自身の自己管理能力も上がっていくと思うんですよね。高校を卒業して大学やプロに行った後、自分で自分の身体を管理できる選手は伸びていきます。個人的に、その部分にもアプローチしていきたいので、コメント欄は活用しています。

――選手達はコメント欄にどのようなことを書いていますか?
サッカーのことについて書く選手であれば、プレーの反省点や気づいたことなどが多いです。身体の構造についてレクチャーをした選手は「腰痛の原因がわかったので、日常生活から意識したい」と書いてきたこともありました。私が見て、身体についての理解が不十分だと思う選手には、コメント欄を使ってアドバイスをすることもあります。こちら側が選手に対してインプットしたものを、選手が正しくアウトプットをすることが大切なので、そのあたりもチェックしています。ケガに関しては予防が大事なので、事前にどのような取り組みができるかを重視しています。『CLIMB DB』を使うことで、体調管理についても、日常生活でこうしたほうがいいよとアドバイスができるので、凄く役に立っています。
河崎護監督のインタビューはこちら