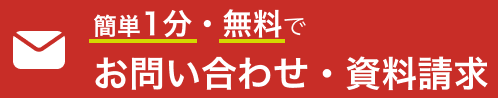東京学芸大学アメリカンフットボール部 SNAILS
東京学芸大学アメリカンフットボール部 SNAILS 平野貴久ストレングスコーチが語る『CLIMB DB』活用法

「『CLIMB DB』でオーバートレーニングを防ぐことができた」
――『CLIMB DB』導入のきっかけを教えてください。
もともと、LINEを使って選手のコンディション管理をしていたのですが、データを集めてパソコンに入力するのが大変でした。何か良いツールがないかと探していたところ、CLIMB Factoryさんのセミナーがあることを知り、『CLIMB DB』を使わせてもらったのがきっかけです。我々が必要だと感じている、メディカル、ストレングス、ニュートリションのデータを効率的に管理することができると思ったので、チームに話を持ち帰り、導入することにしました。
――『CLIMB DB』を使ってみて、どのあたりに良さを感じましたか?
トレーニング記録やフィールドテストの結果を一元管理できて、データを簡単にシェアできるところです。動画を共有できるところもいいと思います。欲しかったデータが集約されているので、管理がかなり楽になりました。使っていて良かったこととしては、オーバートレーニングになりそうな選手を2人、見つけることができたこと。『CLIMB DB』のデータを見ていて、トレーニングの消化率や食事、睡眠の数値が良くない選手がいたので話をしたら、教育実習との両立が大変で、肉体的にも精神的にも疲労が溜まっていることがわかりました。リカバリできない状況になっていたので、トレーニングを休ませたところ、数ヶ月後に復帰することができました。大事にならなくてよかったと思います。

――『CLIMB DB』にデータが蓄積されることで、強化に役立てられることはありますか?
『CLIMB DB』では、週ごとの練習強度をチェックしているのですが、同じ練習プログラムをしても、疲労度がいままでよりも低くなっているといったように、全体の体力レベルを数値化、視える化することに役立てています。
――トレーナーの視点から、『CLIMB DB』のデータを見る際、メディカルやフィジカルなど、どの項目を重視していますか?
身体の気になる部位がイラストで表示されるのですが、そこをチェックしています。なかでも、内科的な症状と筋肉の張りを見ています。ハムストリングが張っていたり、腰が痛い選手が多いときは、トレーニングの内容を変えます。それが大きなケガを防ぐために重要なことだと思っています。とくに春先や新入部員が入ってきたときなどは、トレーニングに慣れていない選手が多く、高強度のトレーニングをしたいときでも、『CLIMB DB』のデータを見て止めておこうという判断をすることもあります。

――『CLIMB DB』を導入した後、ケガ人が減った実感はありますか?
慢性的なケガは減っていますね。ハムストリングの肉離れ、アキレス腱炎、足底筋膜炎など、蓄積疲労が元になるケガは大幅に減少しました。それは『CLIMB DB』を見て、事前にケガをしないような強度設定にしているからだと思います。コーチングスタッフに『CLIMB DB』のデータを見せることで、この選手はこうなんだということを理解してくれるのも大きいです。疲労が溜まっている選手は、出場機会を少なくするなどして調整しているので、練習とリカバリが同時にできるようになっています。
――学生トレーナーが15名ほどいるそうですが、その方たちは『CLIMB DB』をどのように活用しているのでしょうか?
トレーナーはメディカルとストレングス、ニュートリションに分かれていて、ニュートリションは栄養摂取状況をチェックしています。そこに生活習慣を絡ませて、睡眠の質を良くすること、食べる量や水分補給などについてアドバイスをしています。私としても『CLIMB DB』を導入してから、ストレングスの観点からメディカル担当のトレーナーに、この選手を見ておいて欲しいなど、細かく指示が出せるようになりました。チームの全体練習の前に、個人の課題に基づいたトレーニングをするのですが、その強度も『CLIMB DB』のデータと照らし合わせて調整しています。

――トレーニングのしすぎでケガをする選手も多いですからね。
いままでは「練習し過ぎかな?」と思っていても、強度を落とす材料がありませんでした。いまは『CLIMB DB』のデータを見ることで、選手の詳細な体調がわかります。選手達は正直にデータを入力することにしていて、数値に対する基準を作っています。練習後の疲労度なども、トレーナーの立場からすると大事なデータなので、基準を設けることで、チーム内でのバラツキがなくなりました。

――今後の『CLIMB DB』 の活用イメージを聞かせてください。
チーム内の選手の評価基準として『CLIMB DB』の入力率が、スターターとバックアップに分ける際に反映されています。それぐらい、チームで重要な役割を果たしています。選手達は『CLIMB DB』をきっかに、いままで以上にコンディションや食事、睡眠など、自己管理ができるようになってくれればと思います。
齋藤優香トレーナー

毎日、パソコンやスマートフォンで『CLIMB DB』を見ています。日々の調子が顔のマークで出るのですが、それを見て「この選手、大丈夫かな」と気にかけています。体調の移り変わりが、グラフで見られるので便利です。『CLIMB DB』を導入する前は、試合前の筋肉の張りと状態をLINEで聞いて、それを集計してパソコンに入力していました。時間がかかっていたのですが、いまは選手個々が『CLIMB DB』に入力してくれるので、作業が大幅に効率化されました。『CLIMB DB』を見ることで、チーム全体の状態が把握できて、傾向もわかります。それをトレーニング強度と照らし合わせることができるので便利です。試合のシーズンになると、ケガやコンディションの悪い選手が出てくるので、『CLIMB DB』を使って、早めの対応ができるようにしたいです。